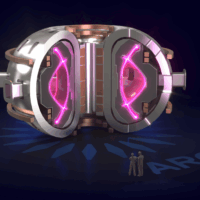日本の教育現場でたびたび話題になる「ブラック部活動」。その実態は、生徒の強制参加や厳しい部則、長時間におよぶ過酷な活動などさまざまな問題を含み、子どもの健全な成長を危惧する保護者たちの間で問題視する声が少なくないようです。他方、近年の政府主導の「部活動改革」では、顧問を務める教員が長時間労働を強いられる点にばかりフォーカスが当たり、急速に進む運動部活動の地域移行(地域スポーツクラブでの活動)に戸惑う声も聞かれます。 そんな中、スポーツ庁が中学校や高校に向けて示す「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(※1)では、部活動について「週あたり2日以上の休養日をとること」「平日は長くとも2時間程度、休業日は3時間程度に」とあり、本来は余暇を豊かにしてくれるはずのスポーツがまるで労働であるかのような印象を受けます。 これらの問題について、体育社会学やスポーツ教育学が専門の社会学部 有山篤利教授は、「スポーツの捉え方から改めて議論する必要がある」と指摘します(※2)。 子どもにとってのスポーツとは、運動部活動とはどうあるべきか。 有山教授と共に、日本の運動部活動の課題の所在と改革の方向性について考えます。
INDEX
ブラック部活動はなぜ生まれた? 社会的背景に迫る

世界とは異なる感覚!? 日本人の多くに共通する「スポーツ観」
(編集部)有山先生は政府主導で進められている部活動改革について、「そもそも抜本的な意識改革が必要だ」と発信していらっしゃいますね。
(有山先生)ブラック部活動と表現される問題には、いろいろな要素が混じっています。昔に比べて子どもの数が激減していますし、価値観の多様化とともに部活動求められる役割も変わってきている。教員不足や働き方改革といった要素も相まって、複雑な様相を呈しています。 そんな中で近年、政府主導で部活動改革が進められていますが、私には上手くいっているようには見えません。関わる大人達が「何のために部活動を改革しているのか」を正面から考えていないように思います。 その原因は、特に運動部活動に言及すれば「なぜ子ども達にスポーツが必要で部活動がどんな役割を果たすのか」というビジョンを共有できてないからでしょう。日頃、いろいろな立場の方とスポーツについて意見を交わしますが、どの世代でも「正しいスポーツとは大会優勝に向け切磋琢磨する競技スポーツのこと」と当たり前のようにイメージする人が多い。私はここに大きな課題があり、意識改革が必要だと考えています。
たしかに競技スポーツもスポーツの一部ですが、スポーツとはもっと広く、包容力のあるものです。「スポーツといえば大会で頂点を目指すもの」とか、「疲れるまで頑張ってこそスポーツだ」とか、そういった偏った捉え方から種々の問題が生じていると考えます。
(編集部)日本の学校で育ってきた私たちから見れば「大会で結果を出すことこそが部活動で行うスポーツだ」という認識でした。
(有山先生)実はそのようなスポーツ観は世界でも異質だといえます。 スポーツは大きく2種類に色分けできます。「競技スポーツ」と「余暇に行うスポーツ(生涯スポーツ)で、日本では前者のイメージが強いですが、欧州ではスポーツといえば一般的には余暇として行うもの。日本で「趣味」と呼ぶような生活を豊かにするものを指します。 たとえば週末にゴルフに勤しむ人や、街中でスケボー、ストリートダンスを楽しむ人も、競技スポーツで上位をめざす人と同じようにスポーツパーソンなんですよ。 余暇を豊かにし生活を楽しむ文化がスポーツで、厳しい修行のようなイメージはない。日本もそのように意識を変える時がきていると思います。
「勝ちのみにこだわる部活動」は日本だけ? 偏狭なスポーツ観、その歴史的背景
(編集部)どうして日本では世界的にも異質なスポーツ観が根付いているのでしょうか。
(有山先生)日本の歴史や国民性が関係していると見ています。 日本に近代スポーツ(野球・サッカー・陸上競技など)が伝わったのは明治維新以降です。明治期に外国人教師によって持ち込まれたスポーツは、いわゆるエリート層の学生たちの間で正課外のクラブ活動として浸透していきました。そして野球の早慶戦に代表されるような学校対抗戦が有名になり、国民的人気を博したのですが……。それが同時に「スポーツ選手が所属団体の看板や名誉を背負って戦う」というロールモデルを育てました。 ヨーロッパではスポーツが個々人のレジャーとして広まった一方、日本では学校対抗の競技大会として広まったのです。
さらに大正・昭和と時代が進み「富国強兵」が国是とされる中、スポーツは欧米に負けない強国を支える人材づくりの教育(体育)として奨励されました。 体は丈夫になるし、厳しいルールは守る、指示はよく聞く。スポーツは便利な存在だったのでしょう。
こうして、日本では学校と競技スポーツが強く結びつくとともに、スポーツとは少なからず頑張りと義務感を伴う活動だとイメージがついたと考えられます。
(編集部)日本の人々にスポーツが広まった当初から、その捉え方が異なったんですね。
(有山先生)加えて、日本の“敗北の記憶”も関係していると思います。日本は過去に2度戦争に敗北しています。1度目は第二次世界大戦という武力による戦争、2度目は戦後の高度経済成長を経て平成初期のバブル崩壊でピリオドを打つ経済戦争です。 これら敗北の記憶を巻き返し、日本に希望を与えたもの。それがスポーツでした。 戦後復興のシンボルとなった1964年の東京オリンピック。敗戦国の日本が欧米を打ち負かす唯一の希望がスポーツという手段で、選手達の活躍に日本中が熱狂しました。そこで競技スポーツへの一種の信仰のようなものが生まれたのだと思います。
その後、経済戦争の最中では成果を上げる人こそが立派とされ、体力と踏ん張りのある運動部活動出身者は特に重宝されました。 当時は「24時間戦えますか?」なんてコピーが流行したりして、成果やお金が手に入れば、プロセス=日々の生活は犠牲にしても止むなしという風潮もあり……。これって、「体育会系」と揶揄される文化と同じだと思いませんか。楽しい学生生活を捨てて、全国優勝を目指すんだ!みたいな。
私は、当時の価値観を否定はしません。我々の親世代はそういう価値観の中を生き抜いてきたし、先人の頑張りが先進国としての日本の成長を後押ししたことは確かでしょう。 でも、時代とともに価値観は劇的に変化しています。
求めるものが変わった。推し活から気付かされるココロの時代の多様性
(編集部)価値観の変化とは?
(有山先生)スポーツに限らず、人々の暮らしに全体において、成果よりも過程の充実が重視されるようになりました。 たとえば学校教育では思考するプロセスを重視するアクティブラーニングにシフトしていますし、趣味の世界でも、「会いに行けるアイドル」として人気となったAKB48は「推し」という言葉を広め、ファンがアイドルの歌(コンテンツ)だけを消費するのではなく、応援する毎日(プロセス)を楽しむ「推し活」が定着しました。
こういった価値観の変化を受け、スポーツ選手も、金メダルを狙うことは目標にしつつも、メダル獲得までの日々の充実や満足感を大切にするという価値観が広がりつつあります。 それなのに、日本のスポーツの捉え方自体はいまだ変化していない。スポーツとは結果を出すために頑張るもの、苦しいもの。そう考えていませんか。 運動部活動についても同じです。子どもは「あんな苦しいことを土日に金払ってやるのか」と考え、大人は「あんな苦しいことを地域に押しつけるのか」と思い…出だしからボタンの掛け違いです。 こういった歴史的背景、価値観の変化を見つめて「今の日本に必要なスポーツとは/部活動とは」という根本的な検討が求められるのに、それがなおざりになっているから部活動改革が進まないのではないでしょうか。
運動部活動改革を成功させるカギ。まず必要なのは戦術よりも戦略

ブラック部活動をとりまく4つの要因
(編集部)スポーツや部活動が果たすべき役割は変わっている。そのことを前提に、改めてブラック部活動問題を含め、現在の運動部活動が抱える問題を考えてみたいと思います。
(有山先生)これらの問題には、次の4つの要因が絡みあっています。 ①人口減少による学校規模の縮小 ②ライフスタイルの変化による教員の働き方改革 ③成果や勝利を至上とする前時代的な部活観 ④価値観の多様化によるニーズの変化
部活動改革が必要な直接の問題は①にあります。単純に子どもの数が減り、野球やサッカーなど団体競技のチームをつくることが難しいところも少なくない。教員の数も減っていて、学校が競技スポーツを担うという制度が疲労を起こしている。 ところが、ブラック部活動問題はいつの間にか教員の働き方改革の問題だけにすり替えられ、学校外の総合型スポーツクラブ等への「地域移行」などの議論だけが進んできました。 そこに部活動改革の推進が重なり、誰もが「何のために部活動を改革しているのか」を理解しないまま迷走しているように見えます。
(編集部)政府は「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(2018年)を出し、目指すところは示しているように見えますが、違うのでしょうか。
(有山先生)掛け声だけで中身がないですね。ガイドラインの前文では、部活動について「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤である」と提議していますが、その中身は旧態依然の苦しいスポーツの継続です。ねらいと中身がずれすぎています。
今回の問題に限った話ではないのですが、日本のこうした改革では、「戦術」は強いのに「戦略」が弱いんです。ここでいう戦術とは問題解決の具体的アクション(How to)のことで、戦略は目標や方向性(Why、What)のことです。 運動部活動改革においても、「それが果たす役割は何?」から始まる戦略が必要なところに、いきなり地域移行という「現状をどう変えるか」の戦術から挑んでしまっている。 これでは現場は混乱しますし、「移行とは何事だ、地域は学校の代替物ではない」と不要な摩擦も生んでいます。 文部科学省の計画では、2023年から2025年までが休日の学校部活動の段階的な地域連携・地域移行を進める「改革推進期間」、2031年までが「改革実行期間」と位置づけられていますが、現場を担う教育委員会の方に話を聞くと「ゴールが見えないが前に進むしかない」といった状況のようです。
運動部活動改革を成功させるカギは、学校教育として役割を明確にすること
(編集部)有山先生が提案する部活動改革の戦略はどういったものでしょうか。
(有山先生)私が提唱しているのが、「学校の部活動は競技ではなく、余暇スポーツの育成を担おう」というものです。
現在、部活動の地域移行が進んでいますが、生徒たちの居場所を教育現場から安易に手放していくことには疑問が残ります。というのも、部活動は生徒にとって自宅や教室と異なるサードプレイス(第3の居場所)の一面があります。 「友だちがいるから」という理由で部活動を続けている子は意外と多く、そういう子達にとっては部活動の内容よりも「そこに居場所があること」が重要。部活動自体は、学校の中に必要なものなんです。
その上で、プロセスを楽しめる部活動としてのあり方、学校規模の縮小や教員の働き方改革といった課題を含めて考えると、ハードな規則や目標に縛られるスポーツ競技である必要はまったくない。 重要なのは、競技スポーツと余暇のスポーツの違いを認識して、学校は「余暇スポーツ」に向けた教育に舵を切ることです。
イメージとしては大学のサークル活動ですね。自分たちでスポーツを楽しむ姿。主体的な遊びができる子どもを育てるのが、部活動の役割だと思います。 そして顧問の教員は、主体的にスポーツをする姿勢を導く存在であってほしい。スポーツって楽しいんだ! と実感し、「教えてもらう」人から「主体的に楽しめる人」へと生徒を変貌させて欲しいのです。そうすれば、部活動はガイドラインが示す「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現する資質・能力を育む基盤」を実現できます。
(編集部)その戦略を実現するために、どういった戦術が考えられますか。
(有山先生)実現のためのアクションとして取り組める課題は主に2つ。 1つが、現在学校で担っている競技スポーツを協会など学校外の外部組織主導で行うこと。現在でも地域にサッカーや水泳、体操などのクラブがありますが、競技として上をめざす選手を強化するのは競技団体の担う役割です。もちろん、学校でも私学など可能なところは、これまで通りそういう場所を用意してあげればよいと思いますが。 2つめが、余暇のスポーツを学校と学校外が連携して浸透させることです。地域移行などといって地域に任せきるのではなく、学校でスポーツを主体的に活用できる人を育成し、地域で機会と場所を準備するような連携が大切だと考えています。
人生100年時代。今こそ求められるマインドセットの変化

スポーツの楽しさを教えることは、人生を楽しむ手段を教えることと同義である
(編集部)有山先生の提言は、部活動の存在は残しつつ、中身と目的を変えるということですね。余暇スポーツが与えるメリットは、ガイドラインにもある「人生において豊かなスポーツライフを楽しめるようになる」のイメージでしょうか。
(有山先生)そうです。今や、人生100年時代。余暇が増大し、ウェルビーイングやクオリティ・オブ・ライフが重視されるようになりました。余暇の遊びは人生を豊かにする「ポジティブな活動」と考える必要があります。 20世紀初頭に活躍したオランダの歴史学者ヨハン・ホイジンガは、人間を「ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)」と捉え、遊びは文化や社会を形成する人間の根源的な活動だと位置付けました。今、この考え方を再評価すべき時代が訪れていると思います。
昔に比べて日々の労働時間や学校の拘束時間は減り、さらに現役引退後の老後時間も寿命とともにどんどん延びる。余暇の過ごし方を知らない大人は、自発的に楽しむ術を持たず、ダラダラと過ごす時間を持て余すと思いませんか。 人生において遊ぶことの重みが今までの時代とはまったく違うと思うんです。 私たちは「遊び=非生産的なもの」という意識を変え、人生100年時代の余暇を変えていく必要がある。となると、子どもの頃から「遊び方」をしっかり教えておいてあげることは重要です。生きる上で欠かせない心と体の健康も手に入る。スポーツを楽しむ感覚は価値が非常に高い。子どもにスポーツの楽しさを教えるなら、余暇スポーツはうってつけです。
(編集部)部活動はその舞台として、大いに活きそうですね。
(有山先生)今ある学校制度を生かさない手はありませんからね。人生100年時代に向け、部活動でスポーツという古くて新しい遊びを手に入れるのです。それこそが部活動改革の意義だと思います。 子どもたちに必要とされるのは、スポーツを一生楽しむための出会いであり、真剣に遊ぶ体験です。スポーツにも多様性が求められる時代、教育現場からボトムアップで余暇を楽しむような生涯スポーツが浸透していくことを望みます。
(編集部)そうなると、従来の「スポーツ=競技スポーツ」というスポーツ観からの脱却は喫緊の課題ですね。
(有山先生)でも、日本が明治以来つくり上げてきた「競技スポーツ信仰」ともいえるスポーツ観を、数年で変えるなんて無理があります。だから私は教育を特に重要視しています。 体育授業を変える、運動部活動を変える。 この課題に挑もうと考えた時、気の長い話でも、まずは人をつくるところから始めないといけないと思いました。そのために専門領域の中でも体育社会学とスポーツ教育学をメインにし、スポーツを「真剣に遊ぶこと」と理解できる人材の育成に尽力しています。
追手門学院大学ではスポーツ文化論やスポーツ教育学を教えていますが、10代・20代の若い学生は柔軟な姿勢で理解を示してくれます。彼ら・彼女らが新しいスポーツ観を周囲に話し、いずれお父さんお母さんになって子どもに伝えて……。みんなの感覚が少しずつアップデートされていけば、今の子ども達が大きくなる30年後くらいには、スポーツ観も大きく変わっているはず。 真剣に遊ぶことの大切さ教える重要性と、真剣な遊びが豊かな人間性の形成に貢献すること。今の現役世代の人には、まずはこういう考え方があるのだと気付いてほしいですね。
まとめ
運動系の部活動と聞いて思い描く「勝利をめざす」「厳しい」といったイメージ、それは歴史的・社会的な背景から固定化されてきたものだったとわかりました。 これまでブラック部活動問題や部活動改革を議論するにあたり、教員の方々の働き方改革や地域資源の活用といった話題に焦点が当たってきましたが、その偏った議論こそ私たちは問い直す必要があるようです。 もっと根源的な「スポーツ本来の楽しさ」を認識し、生涯にわたって楽しめることを子ども達に気付かせるような教育や体験が求められているのでしょう。保護者を含め、大人世代の私たちこそ、スポーツに関するマインドセットを変える時に来ているのではないでしょうか。
【関連記事】